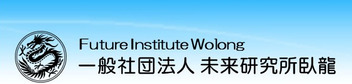設立5周年記念公開パネルディスカッション
おかげさまで、一般社団法人未来研究所臥龍は、2025年8月5日で設立5周年を迎えます。この間の皆様のご支援に改めて感謝申し上げます。
例年通り、周年事業として、本年も公開でのパネルディスカッションを開催いたします。
テーマは「認知症ケア最前線―その可能性」です。
日本では高齢化の進行に伴い、認知症の人の数が年々増加しています。2025年には高齢者の約5人に1人が認知症になると推計されており、社会全体での理解と対応が急務となっています。認知症は単なる医学的問題にとどまらず、本人の尊厳や生活の質、家族や地域社会との関係性にも深く関わる重要な課題です。
今回のシンポジウムでは、「認知症ケアの最前線」と題し、アカデミア、医療・介護現場、創薬研究、シンクタンクなど多様な分野の第一線で活躍する専門家をお招きし、最新の知見や実践的な取り組みについて共有します。薬物療法や非薬物的アプローチ、早期診断の意義、在宅や施設における支援体制、多職種連携の可能性、さらには認知症と共に生きるための地域づくりなど、多角的な視点から議論を深めてまいります。
認知症を「支える」から「ともに生きる」社会へ──その実現のためには、専門家だけでなく地域住民一人ひとりの理解と協力が欠かせません。本シンポジウムが、未来の認知症ケアのあり方をともに考え、共感と連携の輪を広げる一助となることを願います。
第1部では、日本の認知症研究の第一人者である岩坪威先生に基調講演をお願いしました。
皆様ご案内のように、岩坪先生は、神経変性疾患の分子メカニズム解明と治療法開発の世界的第一人者であり、アルツハイマー病におけるアミロイドβの病態的意義を初めて実証し、日本版ADNI(J-ADNI)や全国規模の臨床研究ネットワーク構築を主導されてきました。臨床と基礎、ケアと創薬を結ぶ「橋渡し研究」を力強く推進し、認知症ケアの革新と社会実装に貢献を続けておられます。
基調講演では、その豊かな知見をもとに、医療・介護・地域社会をつなぐ視座から、持続可能な認知症ケアの未来像について伺うことができると思います。
続く第2部では、認知症ケアの現場、創薬研究開発の現場、そして政策研究・提言に携わるシンクタンクから3名のパネリストからそれぞれの実践をご紹介いただき、その後、岩坪先生にも加わっていただいて、認知症ケアの目指すべき方向とその可能性について、忌憚のない討論を行っていただきます。